回復期リハビリテーション看護師認定について
看護師 回復期リハビリテーション
当院看護部には回復期リハビリテーション看護師認定3名、メンタルケア心理士1名が在籍しています。それぞれの得意分野の構築とスキルアップを目指して、日々邁進しております。
回復期リハビリテーション看護師認定コースは、回復期リハ病棟において、以下の活動を行うことの出来る看護師を育成することを目的としています。
①患者及びその家族に対する質の高い看護の提供
②回復期リハ病棟における個人、集団、組織に対するリスクマネジメント
③多職種との協働とチームアプローチの実践
認定要件として、
①認定コースの全日程に出席し、レポートの提出により合格の評価を得ること
②認定コース終了後、自らの課題を決めて、全研修終了後 6ヶ月以内に、回復期リハ病棟で行った 4ヶ月以上の実践活動についてレポートにまとめ、期日までに提出し合格の評価を得ること
上記認定要件を満たした者に対して、認定証が交付されます。
2011年認定 病棟看護師 内山治美
平成23年1月に全コース修了、平成24年11月に認定されました。内山さんの4ヶ月間の実践活動レポートの課題は「食事の姿勢」。内山弁「漠然と食事の姿勢を整えよう・・ではなく、基本的な解剖の理解。摂食(食物を口から食べること)と嚥下(取込んだ水分や食物を咽頭と食道を経て胃へ送込む<飲み込む>こと)のメカニズムには、①準備期(食物を咀嚼し食魂を形成する時期)②口腔期(食魂を口腔からのどに送込む時期)③咽頭期(食魂をのどから食道へ送込む時期)④食道期(食魂を食道から胃に送込む時期)で食物の流れがあります。
ただ「食べられない」という観察だけでなく、解剖学的なメカニズムを理解し観察の気付きをしていく、見えない部分の理解をしていきたい」と、奥の深い実践レポートになりました。
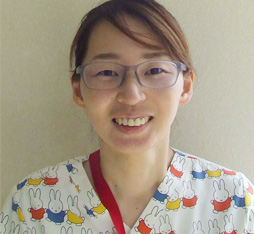
2013年認定 看護部長 松井清美
平成24年1月全コース修了、平成25年12月に認定されました。松井部長の4ヶ月間の実践活動レポートの課題は「看護症例検討会のシステム改善」。部長弁「看護の土台である退院後の生活を見据えた看護介入に焦点をあてました。看護介入ができやすいようにICF(国際生活機能分類図):健康状態・心身機能・身体構造・活動・参加・環境因子・個人因子を用いてアセスメントシートを作成し、患者さんの全体像を把握し看護介入の必要性を理解できるように指導介入し、看護スタッフの意識改革およびスキルアップを目標に、看護症例検討会システム改善を行いました。現在、ICFを取り入れた看護症例検討会は4年目を迎えます。看護師の取り組む姿勢も厚く、あらゆる側面から患者さん及びご家族の情報収集を行っています。どのスタッフが担当になっても格差のない看護が提供できる、退院後「患者さんが自分らしく生活できる」事を目標に頑張っていきたいと思います。」

2023年認定 病棟看護師 谷口 紗恵
2022年から回復期リハ看護師の認定資格を取得する為に認定コースの受講及び実践活動をしていましたが、2023年11月に認定資格を取得することが出来ました。私の実践活動は『回復期リハ病棟での共通ツールを使用した退院支援~多職種連携強化に向けた取り組み~』です。退院支援は、退院直前にチームがバラバラで行うものではなく、患者さんが自身の病気や障害を理解し、退院後に必要な医療や看護を受けながらどこで療養するか、どのような生活を送るかを自己決定するための支援です。スムーズな多職種連携を目的とした多職種が共通で使用するシートを作成し、それを活用した活動実践を行いました。共通のツールを使用することで、リハビリや退院支援の進捗状況や情報共有をスムーズに行うことが出来ました。実践活動を通して、患者さんとその家族が在宅や地域で自分らしく、出来るだけ希望に沿った生活を送れるように、患者さんや家族の思いを汲み取りながら、現状だけでなく今後の生活をイメージして支援することの重要さに改めて気付くことが出来ました。回復を望む患者さんとご家族のサポートが出来るよう、回復期リハに携わる仲間たちと共にこれからも励んでいきたいと思います!

2011年認定 メンタルケア心理士 病棟看護師 村上美加
「病は気から」と言いますが、心が健康でないと体も病んできます。現代はストレス社会であり、誰でも心が不安定になる要素はあります。ですが、誰かに話すだけで気持ちが楽になったりもします。その目に見えない心の部分を、少しでも理解し患者さんとの関わり、また職場の中で少しでも心が楽になれるお手伝いができたらと思っています。

